
”ボバース”とは?
前回の【本編5】の課題指向型アプローチに引き続き、今回は3つの代表的治療法の2つ目の”ボバース”に対する臨床的な視点で考えます。
【本編5】課題指向型アプローチ(長下肢装具)を臨床から考える
”ボバース”と聞いてどんなイメージを持ちますか?この言葉ほど、臨床のセラピストを悩ませたことはないのではないでしょうか。そして、この言葉ほど、非常にポジティブな印象を持つセラピストと非常にネガティブな印象を持つセラピストに分かれさせたこともないでしょう。
そう、ボバースはそういう意味でも、治療法としてかなり影響力の強い存在であったことは間違いありません。実際に、1つの時代において、リハビリの片麻痺の治療で非常に確立された治療方法でした。
講習会に行ったことがある人は分かると思いますが、学校では習ったことのない言葉を使って講義し、実際の入院している患者さんの治療をデモンストレーションとして行い、患者さんの状態を良くしていく姿を見せる。かなりインパクトがあります。
そして、参加しているセラピストは、ハンドリングという徒手的な操作の実技を行っていく中で、難しさを実感していきます。ある人は自分はまだまだだと没頭し、ある人は理解できなくて完全拒否状態になってしまいます。そんな印象を”ボバース”に持っているのではないでしょうか。
臨床におけるボバースの治療法の”本質”とは?
私も、臨床経験が浅い時期は非常に頭を悩まし、どちらかというとネガティブな印象を持っていたかもしれません。でも、そこは仕事なので、なぜか?なぜか?を自問自答しながら進んでいたように思います。
でも、今は、ADL訓練が重視されている時代だからこそ、ポジティブな印象を持っています。
患者さんに対して非常に丁寧な触れ方をします。
ボバースの本質は、”患者さんを丁寧に触れ、丁寧に動かす。筋肉の反応を大事に感じ取る”という点です。特筆すべきことです。セラピストの手という非常に繊細なことを感じ取れる身体部位を最大限に生かしています。これは、なかなかすぐにできることではないです。経験年数が上がれば上がるだけ、重要に感じるようになりました。
もう少し専門的に書くと、患者さんの筋肉の反応を感じ取りながら、セラピストの手によって末梢部から中枢部をコントロールしていく、そして中枢部の安定性向上を図る、という点がボバースの特徴です。”中枢部=体幹”に注目した点は、非常にオリジナルな視点です。そして、”筋の反応”や”追従”といった言葉・概念を臨床に浸透させました。
ボバースの”問題点”をどう考えるか?
ボバースの講習会でも、熟練したセラピストが患者さんに触れて動かし、できなかった歩行などの動作をできるようにさせることは、非常に感動します。でも、そこで考えを止めてはいけません。
”非常に冷静な、客観的な視点で物事を捉えるべき”です。あのセラピストの手を離れた時に患者さんは同じように動けるのだろうか?と考える必要があります。病棟に帰ってからも同じようにできるのか?と。
そう、ボバースの問題点は、”セラピストの手から離れても効果は持続しているのか?、患者は学習しているのか?”ということです。もし、学習できていれば、患者さんは同じことができる(=再現できる)はずです。
熟練したセラピストが治療している時、つまり、その場では良くなるが、また元通りに戻ってしまうでは意味がありません。この点は、ボバースが非常に影響力のある治療法だっただけに、とても指摘されていたところです。
ただ、ボバースの方法論上、これをクリアにすることは難しく、脳卒中ガイドラインでも否定的に書かれたこともあって、ボバースそのものが非常に否定されることになってしまった。良い点もあるにも関わらず、です。これは、臨床の現場でも同じで、かなり影響力が落ちてしまいました。
ボバースの問題点である”患者の学習”に関しては、脳の学習における知識が必要ですが、この点は認知運動療法の考え方を取り入れない限り解決しないでしょう。
次回は認知運動療法(現在:認知神経リハビリテーション)に対する臨床的な考察をしたいと思います。
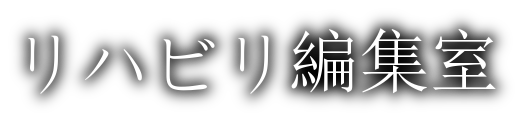

コメント